横浜関内駅徒歩1分/「相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営
開業31年の豊富な経験と確かな実績
横浜 相続・終活支援センター
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!
日本人の相続・遺言
在日中国人、在日韓国人の相続・遺言
営業時間 | 10:00~17:00 |
|---|
その他 | ご訪問も可能です |
|---|
遺言書作成

こちらでは、横浜 相続終活支援センターの遺言
作成について紹介します。
遺言は、残されたご家族への愛のメセージです。
誰にでも最期の時は訪れます。「相続問題で争わないようにしたい」と誰もがそう望みますが、実際「争族」と言われる状態になってしまうことも少なくないのです。
備えをしておけば、そんな争いは起きなかったかもしれません。そして、心配な気持ちが軽くなるかもしれません。
無用な親族間の争いを回避するために、
相続を争族にしないためにも遺言書の作成をお勧めします。
遺言書は、究極のプライバシー情報です。その内容は、誰にも知られたくないものです。
しかし、専門家に相談などしないでご自分一人で作成した自筆証書遺言では、内容がいい加減だったり、形式を間違っていて遺言書として効力が生じないことがあります。
遺言書は、法定の形式に従わないと無効となり、また、中途半端な遺言書のために、かえってトラブルを生じることもあります。
遺言書の作成は、専門家にお任せすることをお勧めします!
大急ぎで遺言書を作成して欲しいとのご依頼が多くあります。
ご相談を頂き、翌日には戸籍謄本等を含む必要書類を収集し、遺言者の入院先等でのご本人との面談を行い、3日目には公証人と共に再び入院先へご訪問をして公正証書遺言を作成します。
最短の場合、午前中にご依頼を頂ければ翌日には公正証書遺言書を作成することが可能な場合もあります。
まずはお電話下さい。
遺言書作成サービス
遺言の種類

いわゆる「遺書」と「遺言書」の違いは、法律で要件が決められているか、決められていないかの違いです。
遺書は、形式も内容も自由に書けますが、遺言書は、
民法で書き方が定められていて、一定の内容(「遺言事項」といいます)には法的な効力が発生します。
遺言には通常、次の3つの方法があります。
★公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとで公証人により作成される遺言。
作成には費用と時間が掛かりますが、遺言書の原本が公証役場に保管されるため改ざんや隠匿等されるおそれが無く安全です。
家庭裁判所の検認手続を受けることも必要がないため相続開始後の名義変更手続きをスムーズに行うことができます。
★自筆証書遺言
全文、作成日、氏名を自分で書き、押印して作成された遺言。
費用が掛からず手軽に作成することができる反面、要件を具備していないと無効となり、偽造、変造、紛失、隠匿、不発見のおそれもあります。相続開始後、家庭裁判所の検認手続が必要です。
☞遺言書はこちら
★秘密証書遺言
遺言者が証書に署名押印し、証書を封じて証書に用いた印鑑で封印し、公証人及び証人2人以上の立会のもとに、この封書が自分の遺言書である旨及び筆者の氏名と住所を述べ、公証人が遺言者の申述と日付とを封紙に記載し、遺言者及び証人とともに署名・押印した遺言書です。
これ以上の手続きはできません。助けて下さい!

横浜市在住の洋子(仮名)さんからご依頼を頂きました。
「先日、93歳で亡くなった叔母は、生涯独身で子供はいません。叔母の両親は既に他界しており、相続人は9人の兄弟姉妹ですが、私の母親以外はみな亡くなっています。叔母の戸籍を取ろうとしましたが、私にはできません。先生、助けて下さい!」と、相談・ご依頼がありました。
調べてみたところ、亡くなられた洋子さんの叔母様(靖子様(仮名))のお母様(洋子さんの祖母、「あき」様(仮名))は後妻でした。また、靖子様は生後すぐに他家に養子にだされ、その後、離縁をして実家の戸籍に戻り、その後、再び他家に養子に出されました。この養親は、靖子様を養子とした後に、別の養子(はる様(仮名))を迎えています。はる様は既に亡くなられていましたが4人のお子さんがありました。
調査の結果、靖子様の相続人は、洋子様のお母様の他に、靖子様の8人の甥と14人の姪の合計23人でした。洋子様にとってはまったく見たことも聞いたこともない親族の登場でした。
生前、靖子様は「すべての財産は、妹(洋子様のお母様)にあげるよ。」とおっしゃっていましたが、遺言はありません。
この場合に「全ての財産は、妹・孝子(仮名)に相続させる。」との遺言があれば、洋子様のお母様は全財産をだれに遠慮することもなく相続できました。
しかし、遺言がないために見ず知らずの親族との間で遺産相続の協議を行わなくてはならなくなりました。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
遺された者の幸福を考えるうえでも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです!
法定要件(遺言事項は民法で定められています)を満たした遺言を残すためには、
相続・遺言についての専門家にご相談されることをお勧めします。
お気軽にご相談ください。
遺言書があれば・・・

横浜市中区在住のBさんの場合は、母のお姉(叔母)さまが亡くなられ相続が開始しました。
叔母様は、結婚歴がなく子供は居ませんでしたので、甥のBさんの妻・C子さんが叔母さまの老後の世話を長年にわたって行ってきました。
叔母さまは、生前、甥のBさんの妻・C子に全財産を譲ると何度もおっしゃっていましたが、遺言をされることなく亡くなられました。
叔母さまの相続人は、ご存命のお二人の兄弟(お一人はBさんのお母さま)と6名の甥・姪ですが、C子さんは、叔母さまとは血縁関係にないために相続権がなく、甥のBさんもBさんのお母さまがご存命のために叔母さまの相続人ではありません。
生前の叔母さまの意思を実現するためには、その意思を遺言として残しておくことが、遺された家族(遺族)への愛情です。
仲の良い兄弟でも、現実に相続が開始すると・・・・・

Aさんは、夫と横浜市港南区の戸建てに暮らしていました。結婚32年目の一昨年、Aさんの夫は突然の「がん」の宣告を受け、残念ながら半年余り後に亡りました。
夫の相続人はAさんと夫の3人の兄弟です。生前、夫は、自身の相続が開始しても兄弟たちは皆、Aさんのために「遺産を望む」ようなことはないと言っていましたが、現実に相続が開始すると二人の兄弟が夫の遺した預金の相続を主張しました。
夫は、遺言書を作成していませんでした。Aさんは、兄弟たちに預金の全てを渡してしまうと、Aさんのその後の生活が成り立ちません。Aさんの夫は自営業でしたので年金は殆どなく家を売る以外に老後の生活を維持していく方法がなくなってしまうのです。
途方に暮れていたAさんは、友人の紹介で堀尾法務事務所に相談にこられました。
お話をよくお聴きすると、Aさんは、入院中に夫との会話を残した音声テープがあることを思い出しました。
その会話の中で、Aさんの夫は、ご自身が亡くなった後の全財産をAさんに遺すとおっしゃていました。
もちろん、この録音テープが遺言書に代わるものではありませんが、Aさんに対して「一度この録音テープをAさんの夫の兄弟に聞いて頂くこと」をご提案しました。Aさんは、この録音テープをご兄弟に聞かせ、「亡くなられたAさんの夫の生前最後の気持ちである。」ことを伝えました。
その結果、預金全額の相続を主張していたご兄弟も預金を含むすべての遺産をAさんが相続することを了承し相続人全員の合意に基づいて「遺産分割協議書の作成、土地と建物の相続登記、預金名義の変更」と全ての手続きを無事に終わることが出来ました。
遺言を残すことが重要であると思わさせるものでした。
法的には有効な遺言書でも相続手続きができないことがある?

「私は、私の全財産を妻に相続させる。
平成8年7月9日
遺言者 佐藤保(仮名) ㊞」
先般、上記の自筆証書遺言による名義変更(所有権移転登記)のご依頼を受けました。
自筆による遺言は、民法に規定がされていて、「遺言者が全文、日付、及び氏名を自署し押印する。」ことで有効となります。
したがって、上記遺言書は民法上は有効な遺言書です。
しかし、この遺言書では遺言者と登記簿上の所有者の同一性が確認できないために、この遺言書のみを添付して名義変更(所有権移転登記)は、残念ながらできません。
ご依頼者にお尋ねしたところ、平成8年7月に大手弁護士事務所にご相談のうえ、夫婦がそれぞれに上記内容の遺言書を作成されたとのことでした。
遺言される場合は、遺言の有効性だけではなく、自分が亡くなった後に自分の財産等が自分の意志にしたがってスムーズに処理できる遺言でなくては遺言を残す意味がありません。
私は、上記遺言以外にも、沢山の遺言書を拝見してきました。
法的には全く遺言として取扱いできないものや遺言通りの手続を行うことに大変な労力と費用(いわゆる「判子代」)を必要とする遺言書等も沢山拝見しました。
やはり、土地や建物の移転登記を含む遺言の場合は、不動産登記の専門家であり法律の専門家である司法書士に任せることが、重要であり安全です!
お気軽にご相談ください。
手続の流れ
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お問合せ

平日は時間がないという方も
安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。(要予約)
お体の都合等で、事務所まで足を運べない方は、ご訪問も可能ですのでお気軽にごお問い合わせください。
ご相談
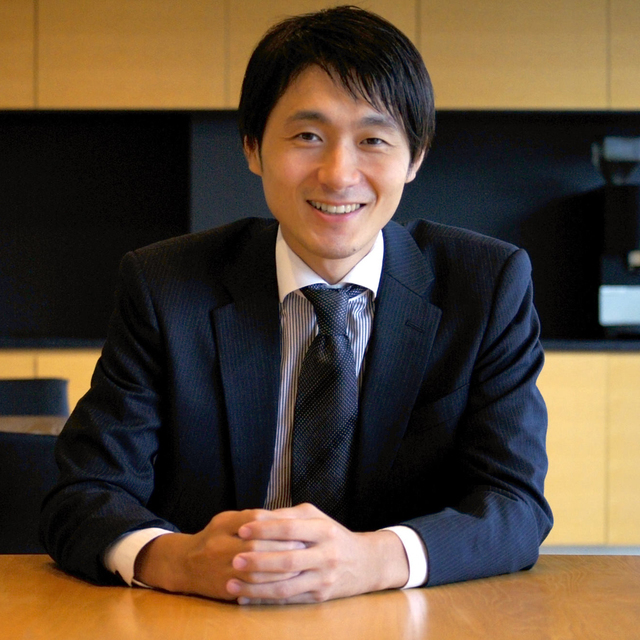
お客さまとの対話を
重視しています。
ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。
ご依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
地元に密着したのアットホームな事務所です。
補助者や事務員による定型的・機械的な業務は行いません。
ご依頼者様お一人おひとりのご事情やお考えを十分にお聴きをします。
ご契約

親切・丁寧
適正料金
横浜 相続・終活センターは、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
報酬やご費用については、必ずご契約前にお見積り致します。
料金表
ここでは基本報酬金についてご案内いたします。
基本報酬料金表(消費税込み)
| 公正証書遺言書作成・手続 | 11万円~(目的財産が1億円迄) 公証人と打ち合わせ,公証役場同席、出張費、日当、交通費の全てを含みます。 |
|---|---|
| 公正証書遺言書の立会証人 | 1万1000円~(証人1人につき)×人数 公正証書遺言の場合には、2人以上の立会証人が必要です。 当事務所にて立会証人を手配することができます。 |
| 自筆証書遺言書の検認手続支援 | 5万5000円~(1通について、相続人調査、日当、交通費を含むお値段です) |
| 遺言執行 (遺言執行者に就任して遺言内容を実現します) | 相続財産1000万円以下の場合 |
市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にご相談ください。
その他のメニュー
お問合せはこちら
ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
お問合せはこちら
ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください。

お電話でのお問合せはこちら
0120-569-567
045-651-3324
●住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階
JR関内駅南口 徒歩1分
地下鉄関内駅1番出口 徒歩1分
●営業時間
10:00~17:00
●休業日
土曜日・日曜日・祝日
事前予約で土日・祭日、
営業時間外も対応可能
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
個別相談会開催
➡詳しくはこちらを
遺言・相続・終活のご相談や手続は、横浜市中区の堀尾法務事務所が運営する「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
事務所概要はこちら

0120-569-567



